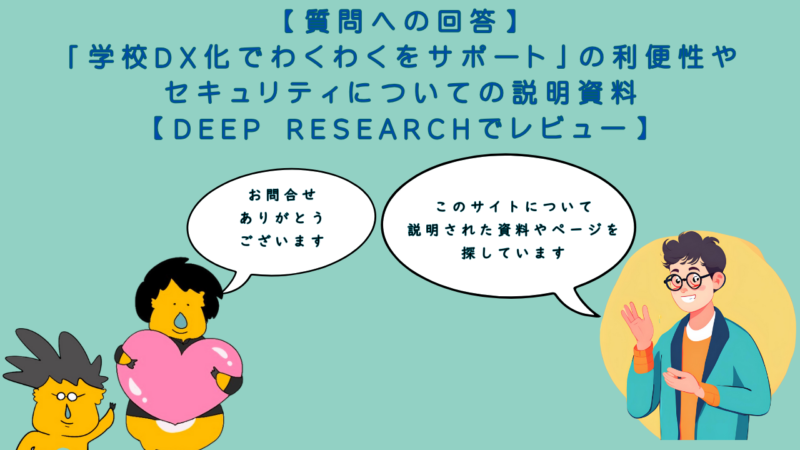

このようなお問合せをいただきましたので、当サイトの利便性について
ChatGPTのDeep Researchで、調べてもらいました。

現場の先生方にこのサイトの存在を広めたいと思っています。
ただ、所属自治体では生成AIの活用に対して慎重な姿勢があり、教職員が業務で使用できる生成AIの種類も限られているようです。現場での利用を広げていくためには、まず管理職に相談してみようと考えています。
そこで、このサイトについて説明された資料やページを探しているのですが、全体像を示すような資料があればと思い、連絡いたしました。
もしご提供いただける資料や情報がありましたら、あわせて教えていただけますと幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。
はじめに
学校の管理職の皆さま、最近話題の**生成AI(Generative AI)**を授業や業務に活用したいとお考えではないでしょうか? 例えば「ChatGPT」のようなAIは便利そうだけれど、情報漏えいやプライバシーが心配だったり、コストや導入手続きのハードルが高いと感じていませんか。
実は、熊本大学の研究プロジェクトから生まれた 「学校DX化でわくわくをサポート」というウェブサイトでは、教育・支援現場で誰でも手軽に使える生成AIツールが提供されています。しかも無料・登録不要で利用でき、安全面にも十分配慮されています。本記事では、この「学校DX化でわくわくをサポート」の特色や技術的なポイント、安全性、利便性について、学校の管理職向けに丁寧かつ親しみやすく解説します。校内への導入を前向きに検討できるよう、ぜひ参考にしてください。
サイトの特色と目的: 教育現場のための生成AIプラットフォーム
「学校DX化でわくわくをサポート」は、熊本大学教育学部の特別支援教育研究室(本吉研究室)が運営する、授業・教材研究を支援する情報プラットフォームです。最新のデジタル技術やAIを特別支援教育をはじめとする教育現場に応用することを目的としており、2023年から教員の業務支援や教材開発に関する様々な取り組みを行っています。このサイトでは、その研究成果として複数のAIチャットボットが公開されており、教師や支援員の皆さんが日々の業務や授業で活用できるよう工夫されています。
特徴的なのは、提供されているチャットボットが教育現場のニーズに特化している点です。一般的なChatGPTのように汎用的な対話をするだけでなく、教育・支援の現場で「こんなことができたらいいな」という用途に合わせたオーダーメイドのAIアシスタントになってくれます。例えば、以下のようなさまざまな機能のチャットボットがラインナップされています。
- プロンプト指導役「プロンちゃん」 – 生成AIを使いこなしたい先生向けのプロンプト作成トレーナーです。AIへの指示文(プロンプト)の作り方を優しく教えてくれて、先生方のAI活用スキルを向上させる頼れる存在です。初めてAI活用に挑戦する先生でも、「こう書けばもっと意図した回答が得られるよ」といったアドバイスをもらえます。多くのコアラちゃんたちが「よろしくね!」と声をそろえ、カラフルな衣装のプロンちゃんが「書き方教えまーす❤」と頼もしく呼びかけてくれるビジュアルも親しみやすいですね。
- 問題作成マシーン「ひらめい太」 – 特別支援教育の教材作成をサポートするチャットボットです。特別支援教育の学習指導要領内容を学習しており、生徒の理解度やニーズに応じた国語・算数・生活科など各教科のオリジナル問題を自動生成してくれます。紙面で工夫していた教材も、このAIを使えば必要事項を対話で入力するだけで、短時間で作成可能です。
- 多言語翻訳アシスタント「ことのは・ソフィア・リンク」 – 国際化が進む中で便利な多言語対応チャットボットです。PDFや画像ファイルなど様々な資料から日本語テキストを抽出し、それを英語をはじめ希望の言語に自動翻訳できます。例えば日本語のお便りを英語や中国語に翻訳して保護者に提供したり、海外の資料を日本語で読む、といった用途に役立ちます。言語の壁を取り除き、インクルーシブな教育環境づくりをAIがサポートしてくれます。
- 要約支援「サマリン&リコリン」 – 会議記録や文章の要約・議事録作成を手伝うチャットボットです。音声認識アプリ「UDトーク」と組み合わせることで、発言内容をテキスト化し、AIが素早く要約文を作成してくれます。煩雑な会議録の作成時間を大幅に短縮でき、公務の効率化に直結します。
以上は一部の例ですが、このように「学校DX化でわくわくをサポート」には多数のAIチャットボットが用意されており、それぞれ教師や支援員の具体的なニーズに応じた機能を備えています (AIチャットボットたちを紹介します! )。サイト上では「AIチャットボットたちを紹介します!」という記事で一覧が公開されており、用途別にどのチャットボットが何を得意としているかが丁寧に説明されています。例えば他にも、学習指導案(指導案)作成を支援するものや、生徒の実態把握をサポートするもの、教材教具の検索を手伝うもの、相談相手になるカウンセラー的なものまで、ラインナップは多彩です。いずれも教育現場のDX(デジタルトランスフォーメーション)を促進し、先生方の負担軽減や授業の質向上につなげることを目指しています。
採用しているチャットボットの種類と特徴: Dify+Geminiによる高度なAI
では、このサイトのチャットボットたちはどのような技術で動いているのでしょうか?実は「学校DX化でわくわくをサポート」のAIチャットボット群は、Difyというオープンソースのプラットフォーム上に構築されています (Difyにおけるチャットボットのインターネット運用とローカル運用)。そして、その頭脳部分(AIモデル)にはGoogle社の「Gemini API」(ジェミニAPI)を利用しています。ここでは少し技術的になりますが、できるだけ噛み砕いてご説明します。
- Dify(ディファイ)とは?
Difyは、開発者がAIチャットボットや生成AIアプリを簡単に作成・公開できるプラットフォームです。専門的なプログラミング知識がなくても、GUI(画面操作)で直感的にチャットボットの構築ができるため、本研究室でもこのツールを使って多数のチャットボットを開発しています。Difyはバックエンドサービス(BaaS)とLLM運用管理(LLMOps)の仕組みを組み合わせており、OpenAIやAnthropic、HuggingFaceなど様々な大規模言語モデル(LLM: Large Language Model)プロバイダーに対応しています。要するに、Difyを使うことで複数のAIエンジンを柔軟に切り替えたり統合したりできるのです。 - LLM(大規模言語モデル)とは?
先ほど少し出てきたLLMとは、大量のテキストデータから学習して人間のように文章を理解・生成できるAIのことです。ChatGPTの背後にあるGPT-4などもLLMの一種ですね。Dify上で動くチャットボットは、このLLMを利用して人間の問いかけに対し自然な言葉で回答します。LLMはまさにチャットボットの「頭脳」に当たります。 - Gemini APIとは?
**Gemini(ジェミニ)**はGoogleが開発した最新のマルチモーダル大規模言語モデルです (Vertex AI における Gemini API のデータ利用について #Google – Qiita)。マルチモーダルとはテキストだけでなく画像や音声・コードなど様々な種類の情報を理解・生成できることを意味します (Vertex AI における Gemini API のデータ利用について #Google – Qiita)。Geminiは高度な推論能力を持ち、文章の要約や分類、対話エージェントとしての会話、コンテンツ生成(文章や画像の作成)など幅広いユースケースに対応できるよう設計されています (Vertex AI における Gemini API のデータ利用について #Google – Qiita)。いわばGoogle版のChatGPTともいえる最先端AIで、教育分野での活用にも大きな期待が寄せられています。「学校DX化でわくわくをサポート」では、このGeminiにアクセスするためのAPI(アプリケーションプログラミングインターフェース)を使ってチャットボットを動かしています。 - Gemini API(有料版)の利用:
GoogleのGeminiは本来有料のクラウドサービス(Google CloudのVertex AI経由など)ですが、「学校DX化でわくわくをサポート」では研究費の支援によって有料版を導入しているため、ユーザーは無料でこの高度なモデルを利用できます。有料版を採用しているメリットは、高性能なモデル(例: Geminiプロ版)による高品質な応答が得られることや、後述する安全性の保証があることです。Geminiには性能や用途に応じていくつかモデルの種類がありますが、サイト内の記事では「Gemini Pro 1.5」を使って生成した回答例などが紹介されており、非常に自然で的確な応答が得られることが示されています。日本語のやりとりにももちろん対応しており、教師とAIの対話もスムーズに行えます。
まとめると、「学校DX化でわくわくをサポート」のチャットボットたちは**「Dify」という基盤の上で、Googleの最先端AIモデル「Gemini」を頭脳として動いている**イメージです。そのため、ユーザーはウェブブラウザ上で普通に質問を入力するだけで、背後では高度なAIモデルが働き、適切な回答や資料の生成を行ってくれるわけです。技術的な仕組みは裏方に隠れているので意識する必要はありませんが、「最新のAI技術が裏でちゃんと動いているんだ」という安心感を持ってお使いいただけるでしょう。
安全性の強調: データ利用ポリシーと他サービスとの比較
生成AIを業務で活用する際、最も懸念されるのは安全性やプライバシーです。特に、校内の機密情報や生徒の個人情報がAIに入力される場合、「そのデータはどこまで共有・利用されるのか?」という不安が生じます。
当サイト「学校DX化でわくわくをサポート」では、以下のような構成でサービスを提供しています:
- Xserver上でDifyを稼働:日本国内のサーバーで運用し、チャットログを安全に管理。
- 有料版のGoogle Gemini APIを利用:ユーザーの入力データをAIモデルの学習に使用しない設計。
- 本サイトにリンクして公開:ユーザーが安心して利用できるよう、明確な情報提供を行っています。
この構成により、個人情報保護とセキュリティの両面で高い信頼性を確保しています。
ユーザーデータを学習に利用しない
Google Cloudの有料版Generative AIサービス(Gemini APIを含む)では、ユーザーの入力データや生成された応答が、ユーザーの明示的な許可なしにモデルのトレーニングやファインチューニングに使用されることはありません。また、Gemini for Google Cloudでは、ユーザーが入力したプロンプトや生成された応答は、モデルのトレーニングやファインチューニングに使用されません。
● 以下は、Google Cloud の有料版 Generative AI サービス(Gemini API を含む)におけるユーザーデータの取り扱いに関する公式情報を基にした説明です。
Google Cloud の Generative AI サービスにおけるユーザーデータの取り扱い
1. モデルのトレーニングにおけるユーザーデータの使用制限
Google Cloud のサービス特定条項の第17条「トレーニングの制限」において、Google は顧客の事前の許可または指示なしに、顧客データを AI/ML モデルのトレーニングやファインチューニングに使用しないことが明記されています。
「Google は、顧客の事前の許可または指示なしに、顧客データを AI/ML モデルのトレーニングやファインチューニングに使用しません。」
(出典:Service Specific Terms | Google Cloud)
この方針は、Gemini API を含む Google Cloud の Generative AI サービス全般に適用されます。
2. Gemini for Google Cloud におけるデータの使用
Gemini for Google Cloud では、ユーザーが入力したプロンプトや生成された応答は、モデルのトレーニングやファインチューニングに使用されません。
「Gemini for Google Cloud は、ユーザーのプロンプトや生成された応答を、モデルのトレーニングやファインチューニングに使用しません。」
(出典:How Gemini for Google Cloud works)
また、Gemini for Google Cloud は、ユーザーの入力や応答を保存しない設計となっており、データはリクエストへの応答のためにのみ使用されます。
3. データのキャッシュと保持期間
Google Cloud の Generative AI サービスでは、パフォーマンス向上のために入力と出力が最大24時間キャッシュされる場合がありますが、これはプロジェクトレベルで無効化することが可能です。
「Google の基盤モデルは、Gemini モデルの入力と出力をキャッシュします。これは、レイテンシを減らし、後続のプロンプトへの応答を高速化するためです。キャッシュされた内容は、リクエストが処理されたデータセンターで最大24時間保存されます。」
(出典:Generative AI and data governance – Google Cloud)
キャッシュの無効化は、Google Cloud プロジェクトレベルで設定でき、すべてのリージョンに適用されます。
4. データの保存場所と地域性
Google Cloud は、顧客のデータを指定された地域に保存することを保証しています。
「Vertex AI の Generative AI 機能に対する新しいデータ居住地のコミットメントにより、Google Cloud の一般サービス条項に従って、顧客が選択した場所に顧客データを保存することを約束します。」
(出典:Google Cloud generative AI data residency guarantees for data stored at rest)
これにより、特定の地域(例:日本、シンガポール、韓国など)でのデータ保存が可能となり、地域の規制や要件に対応できます。
「学校DX化でわくわくをサポート」は、Google Cloudの有料版Generative AIサービス(Gemini APIを含む)とXserver上でのDify運用により、ユーザーの入力データや生成された応答が、ユーザーの明示的な許可なしにモデルのトレーニングやファインチューニングに使用されることはありません。また、データのキャッシュや保存に関しても、ユーザーが制御可能な設定が提供されています。これにより、教育機関や企業が機密性の高い情報を扱う際にも、安心してサービスを利用することができます。
● 人間のレビューやデータ保存について: もっとも、入力内容が全く記録されないというわけではありません。Googleはサービス品質の向上を目的として、一時的に入力や出力を保存し、人間のレビュー担当者が確認する場合があるとも述べています (Vertex AI における Gemini API のデータ利用について #Google – Qiita)。ただしその際もプライバシー保護のため、Googleアカウント情報やAPIキーとは切り離された形でデータが扱われる仕組みです (Vertex AI における Gemini API のデータ利用について #Google – Qiita)。要するに、誰のデータか分からない匿名化された状態で品質チェックが行われる可能性はありますが、モデルの改善素材として再利用されることはないということです (Vertex AI における Gemini API のデータ利用について #Google – Qiita)。また、「学校DX化でわくわくをサポート」自体も研究目的で運営されていますが、ユーザーに断りなく個人情報を収集したり外部に提供するようなことはしていません。サイト利用時に任意のアンケート協力依頼が表示される程度で (最新のサービスを特別支援教育へ! | 学校DX化でわくわくをサポート)、入力した質問内容そのものが外部に公開されることもありません(※公開掲示板ではなく個別の対話システムですので、第三者から会話内容が閲覧される心配はありません)。
● 他の生成AIサービスとの比較: Gemini APIの安全性を強調するために、他の代表的な生成AIサービス「Copilot」とデータ利用方針を比較してみましょう。
- 「学校DX化でわくわくをサポート」で提供されているAIチャットボットは、Google社の有料版Gemini APIを基盤としており、ユーザーの入力データがAIモデルの学習に使用されないことが公式に明示されています。
これは、Microsoftの「Copilot」や「Microsoft 365 Copilot」など、多くの学校で使用が認められている生成AIツールと同等のセキュリティ水準を確保していることを意味します。
たとえば、Microsoft 365 Copilotでは、ユーザーのプロンプトや応答、Microsoft Graphを通じてアクセスされるデータが、基盤となる大規模言語モデル(LLM)のトレーニングに使用されないことが明記されています。 マイクロソフトラーニング
また、GitHub Copilotにおいても、BusinessやEnterpriseプランのユーザーデータはモデルのトレーニングに使用されないとされています。 GitHub+1GitHub+1
このように、「学校DX化でわくわくをサポート」のAIチャットボットは、学校現場での利用において、他の主要な生成AIツールと同等のセキュリティ対策が施されています。
アカウント登録不要で手軽に利用できる点も含め、教育現場での導入を検討する際の一助となるでしょう。
以上を踏まえると、「学校DX化でわくわくをサポート」が採用するGemini API(Google)によるチャットボットは、データの扱いに関して非常に厳格で安心だと言えます。他サービスでは設定変更や有料プランでようやく得られる「入力データを学習に使わない」という条件が、Geminiでは標準仕様として保証されています (Vertex AI における Gemini API のデータ利用について #Google – Qiita)。また、運営母体が大学研究室ということもあり、商用サービスのようにユーザーデータを収益目的で分析・活用するといった動機もありません。教育現場で気になる機密情報の漏えいリスクやプライバシー侵害の懸念を限りなく低減している点は、校内導入を検討する上で大きな安心材料になるでしょう。
利便性: 無料・登録不要で誰でもすぐに使える手軽さ
次に、「学校DX化でわくわくをサポート」の利便性についてです。忙しい学校現場で新しいITツールを導入する際、「使い方が難しくないか」「コストや手続き面でハードルがないか」は重要なポイントです。その点、「学校DX化でわくわくをサポート」は非常に手軽で導入しやすいサービスとなっています。
● 完全無料で利用可能: 「学校DX化でわくわくをサポート」のAIチャットボットはすべて無料で利用できます。これは前述のように文部科学省系の科研費(科学研究費補助金)によってプロジェクト運営費が賄われているためで、ユーザーは利用料を一切支払う必要がありません 。高性能な生成AIモデルは通常API利用料が発生しますが、その部分も研究費でまかなわれており、利用者の負担はゼロです。学校の予算を気にせず試せるのは大きなメリットです。
● アカウント登録不要: 利用にあたって面倒なユーザー登録やログインは一切不要です。「学校DX化でわくわくをサポート」のサイトにアクセスし、使いたいチャットボットのページを開けば、すぐに質問を入力して対話を開始できます。メールアドレスの登録や個人情報の提供も不要なので、試してみたいと思った時にすぐ使えますし、ID・パスワード管理の手間もありません。特に校内で先生方に広く使ってもらうには、「アカウントを作って…」という手順が省けるのは嬉しい点です。生徒に使わせる場合でも、個人情報を登録しないで済むので安心感があります。
● 専用ソフト不要・マルチデバイス対応: 「学校DX化でわくわくをサポート」はウェブサイト上で動作するサービスですので、パソコンのブラウザからでもタブレット・スマホからでも利用できます (Gemini日本語版の始め方・使い方とは?料金や3つの特徴も紹介)。特別なソフトウェアのインストールは不要で、インターネットに接続できる環境さえあれば学校のPCでも自宅の端末でも同じように使えます。たとえば職員室のデスクトップPCで指導案を練る際に使ったり、授業中にタブレットで生徒と一緒に問題を生成してみたりと、シーンに応じて柔軟に活用できます。マルチデバイス対応であることは、昨今のBYODやオンライン学習の流れにもマッチしています。
● 日本語でそのまま使える: 海外製のAIだと日本語への対応具合が気になるところですが、Geminiは日本語を含む多言語で十分な性能を発揮するよう訓練されています (Gemini モデル | Gemini API | Google AI for Developers)。実際、「学校DX化でわくわくをサポート」上のチャットボットは日本語で自然に対話できます。専門用語が出てきても日本語で噛み砕いて説明してくれたり、生成される文章も日本の教育現場になじむ丁寧な文体になっています。英語が苦手な先生でも安心ですし、逆に「英語で返信して」と指示すれば英語回答も可能なので、語学の教材作成などにも応用できます。
● 現場の声に基づく改善: 「学校DX化でわくわくをサポート」は研究プロジェクトの一環として、ユーザー(先生方)のフィードバックを重視しています。サイト上で使ってみて「もっとこういう機能が欲しい」「ここが使いづらい」といった声が集まれば、今後の改良や新チャットボット開発に反映されていくことでしょう。既に2024年後半から2025年にかけて、利用者のニーズに応じたチャットボットが次々と追加・改良されています。このように進化し続けるサービスである点も、導入後の将来性として魅力的です。
以上のように、「学校DX化でわくわくをサポート」はコスト面・手続き面・技術面のどれをとっても利用障壁が非常に低く、学校現場にすんなり溶け込めるよう配慮されています。「無料ですぐ試せる」のはやはり大きな強みで、まずは管理職の先生が実際に触ってみて使い勝手を確かめ、その上で他の先生方にも展開するといったステップが踏みやすいでしょう。
教育現場への導入メリットとまとめ
「学校DX化でわくわくをサポート」は、最新の生成AI技術を現場の先生方が安心して・便利に使いこなせるよう工夫されたプラットフォームです。教育・支援の現場に特化したチャットボットが多数揃っているため、例えば以下のような幅広いメリットが期待できます。
- 教員の業務効率化: 指導案作成の下書きをAIがサポートしたり、会議の議事録を自動要約したりと、日々の事務作業の負担軽減に貢献します。
- 教材作成の質と速度向上: 生徒の実態に合った課題プリントやクイズを短時間で作成できるため、個別最適化された教材を迅速に提供できます。
- 特別支援教育の充実: 特別支援教育の専門的な知識(例: 学習指導要領の内容や自立活動の分類)をAIが参照し、教師をコーチングしてくれるので、支援計画の立案や教材研究がスムーズになります。
- 多様な学習ニーズへの対応: 多言語翻訳チャットボットで日本語が苦手な児童生徒や保護者を支援したり、AIが生徒の質問に答えることで個別学習を促進したりと、学習者の多様性に応じたサポートが可能です。 (最新のサービスを特別支援教育へ! | 学校DX化でわくわくをサポート)
- 教員研修・スキル向上: プロンちゃんのように教員自身のAI活用スキルを高めるトレーナーもいるため、職員研修の一環として取り入れることで教員全体のICT活用能力向上にもつながります。
ご紹介してきたように、「学校DX化でわくわくをサポート」は**「最新技術でありながら現場目線」で作られている点が大きな魅力です。研究ベースのサービスなので商用サービスほどの宣伝はされていませんが、その分安全性や教育的妥当性がしっかり検証**されています。実際、本研究は文科省系の補助金を受けて実施されており、2024年にはICT・AIワークショップ等の場で教員の方々に直接体験してもらう取り組みも行われています。現場の声を聞きながら改良が重ねられているので、教育現場との親和性は今後ますます高まっていくでしょう。
校内導入を検討するにあたっては、まず実際に試しにサイトのサービスを使ってみることが出発点になります。「学校DX化でわくわくをサポート」というコンセプトのもと、職員会議や校内研修、あるいは地域の研修会などで、「ちょっと5分だけ、このAIツールを体験してみましょう」と気軽に紹介することができます。アカウント登録も不要なため、その場ですぐにアクセスして体験でき、準備や手続きに手間はかかりません。
また、導入のきっかけは管理職に限る必要はありません。たとえば、研究部の先生や教務の先生、情報教育に関心のあるインフルエンサー的な立場の先生が先に活用し、「これ、便利だったよ」「こんなふうに使えるよ」といった声を校内で共有することでも、自然な形で広がっていく可能性があります。口コミや日々の会話の中で紹介されることで、教職員全体の関心が高まり、無理なく導入が進められるでしょう。
結びに、学校現場で生成AIを活用することは今後避けて通れない流れかもしれません。しかし大切なのは、ただ流行りに飛びつくのではなく、安全で信頼できる形で導入することです。「学校DX化でわくわくをサポート」はまさに教育現場のために考え抜かれた生成AIツールですので、そうした条件に適っています。ぜひ一度、このサイトのAIチャットボットたちに触れてみてください。「AIってこんなことまで手伝ってくれるんだ!」という驚きと、「これなら校内で使っても大丈夫だ」という安心感を得られることでしょう。学校DXの心強いパートナーとして、「学校DX化でわくわくをサポート」の活用を前向きに検討してみてはいかがでしょうか。
参考資料・出典: 本記事では熊本大学本吉研究室「学校DX化でわくわくをサポート」サイト内の記述や公開資料、および各種サービスの公式情報等を参照しました。特にGemini APIのデータ利用ポリシーについてはGoogleの公式ドキュメントを、他サービス(ChatGPTやCopilot)の事例については有志による技術ブログやニュース記事を元に比較検討しています。詳しくは本文中の引用箇所をご参照ください。
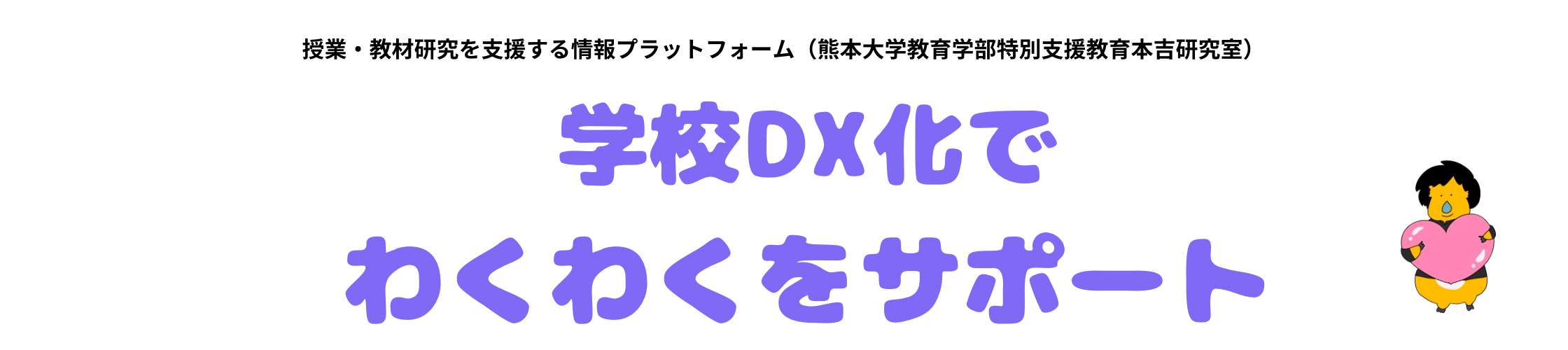
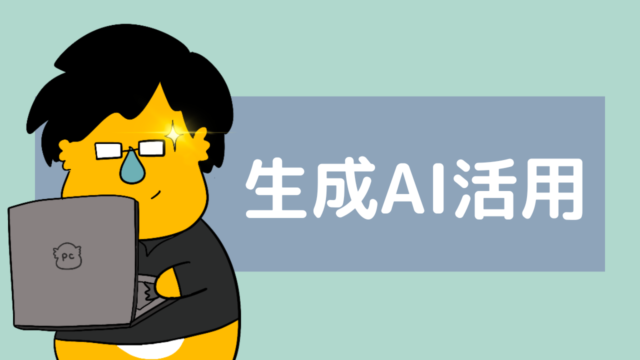


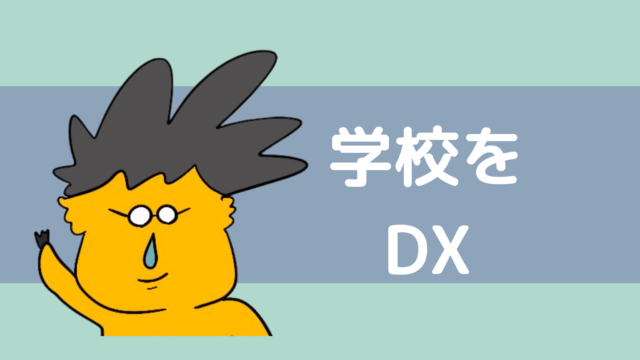

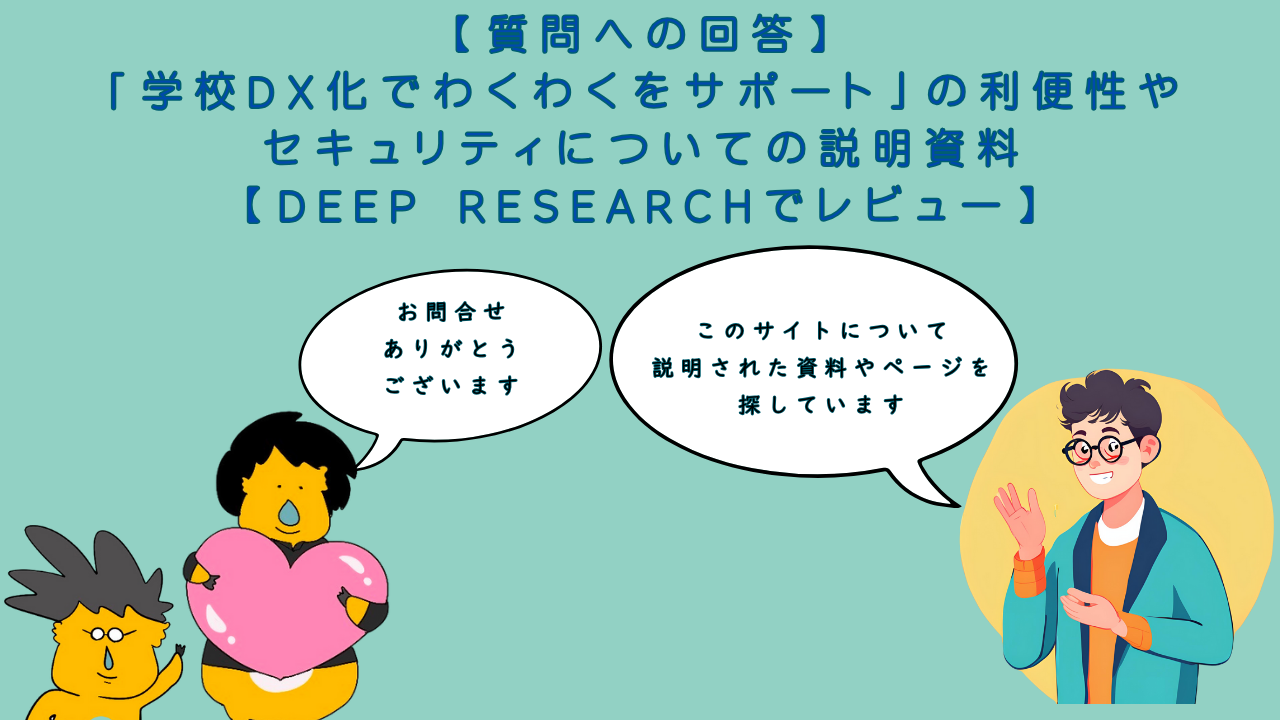
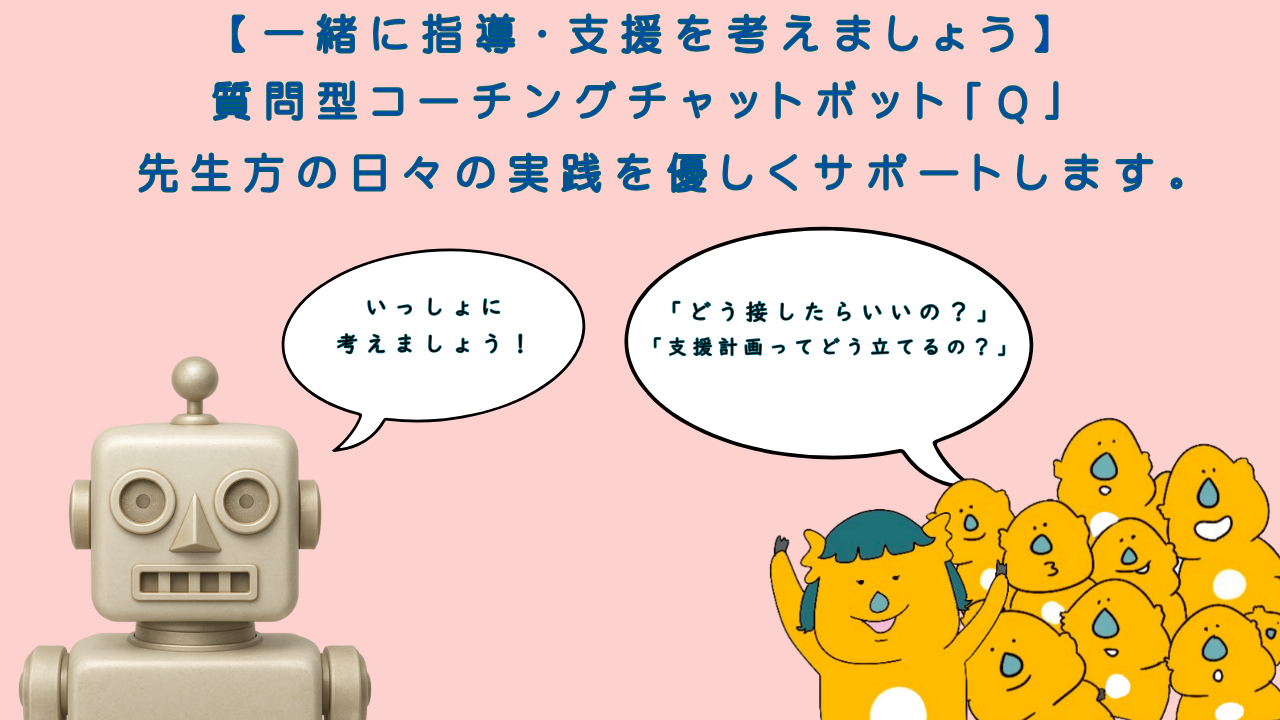
コメント